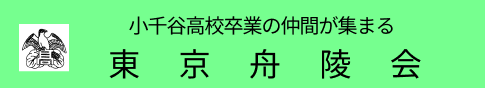一度だけの句会
雁木行く何を怺(こら)ふる顔のみぞ 志城柏
この句は、『散木抄』中の志城柏句稿・貳の第十一句となっているので、お目に留められた方も多いだろう。しかし、私はと云えば、送って頂いた『散木抄』の冒頭に連なる目﨑徳衛先生自選の百八句の中に本句を見つけた時には、数十年前の記憶がよみがえって、興奮を禁じ得なかった。小千谷高校時代に、自分にとって一生に一度となった句会で、先生が詠まれた句だったからである。ある日、谷高図書館の事務室に入ろうとして、半分ドアを開けた時、「じゃあ、それでよろしいですか、先生。」と、念を押す司書担当の田近正司先生のお声と、「良いですよ、日にちと場所を決めておいて下さい。」と答えて、ニコニコしておられる目﨑先生のお声が聞こえた。私が事務室に入るのと入れ替わりに、目﨑先生は次の講義のために事務室を出て行かれた。それまで、目﨑先生が座っておられた田近先生の隣の机を見ると、A5版・厚さ5ミリ位の奥付も無い小冊子が置いてあった。「それは、先生の学生時代の親友が送って下さって、昨日届いていたんですよ。 だから先生のご機嫌がとても良いので、句会でのご指導をお願いしておきました。君も出席するといいですよ。」
誰が企画したのだろうか?田近先生か、図書部長の久世先輩か、はたまた図書部員の誰か、か。私は、聞いていなかったので、田近先生には曖昧な返事をして、その小冊子を手に取り、しばらくの「授業時間つぶし」のつもりで目を通すことにした。当時、教科書を読むだけのような教師の授業はサボって、図書室で新入庫本などを読むことが時折あったのである。[補遺1]その冊子表紙には、「無用者の系譜 唐木順三」とあった。当時既に文芸評論家として名を馳せていた唐木順三という著者のことも知らずに、漫然と目を通していった。そして、「平城天皇の孫という高貴な血筋に生まれながら、高い官位を与えられず、重職にも就けなかった在原業平という中年貴族が、身を用(要)なき者に思ひなして旅にでる」などという内容には、ああ、世捨て人の逃避行を書いているだけか、というような感想しか抱けなかったから、目﨑先生がなぜあんなにご機嫌が良かったのか、理解しないままに、「分りました。出るようにします。」と田近先生にお答えして次の授業のために図書室を退出した。[補遺2]
出席を約束するとお答えしたものの、実はあまり気が進まなかった。目﨑先生には、日本史の教えを受けていたが、志城柏と号する俳句の泰斗であられることを、多くの生徒は知らなかった。折角だから、俳句のご指導を頂く機会も作って頂いてはどうかという提案だったのだろうが、生徒の間でそんな希望が出ていたとは思えず、参加者は数人にとどまるのではないかと思ったからである。気が進まないもう一つの理由は、その頃、私がある短歌の会に通っていたことにあった。中学時代の国語の恩師・河本茂先生に誘われて、歌会に足を運ぶようになってから三年目に入っていた。月に一度は、長岡で開かれる集まりに連れて行って貰っていた。新潟大の一講師が主宰されていて、情熱的な人たちばかりの集まりで、歌風は与謝野晶子ばりのものが多かった。しかも、二ヶ月前の会で、私の歌が初めて一席に選ばれたのだが、それは、
新しき渇きはなおも満たされず 雨は私をよけてふります 邦夫
というもので、今読めば何とも気恥ずかしいが、主催者に「なおも」というような安易なつなぎは無い方がいいですね」と批評されても、いささか有頂天になっていて、「俳句は年寄りの手遊みじゃないの」くらいにしか考えていなかったのである。しかし、句会は開かれた。授業が比較的早く終わる曜日の放課後、節電のため電灯を消した少し暗い部屋の一つに、二十人強の生徒が集まった。大部分は図書部員だったと記憶している。先生はまず「今から1時間で、俳句を詠んでみて下さい。学校の周辺を散策してもいいし、この教室でじっくり考えてもいいですよ。」と指示された。数人が教室に残り、私もその一人だったが、やっとできた句は、記録が無いので定かではないものの、次のようなものだった。
土器ありと雉はしきりに嘘をつき 邦夫
数ヶ月前に、父から「土器が出るという丘があるから、散歩に行こう」と誘われて出かけたことがあった。父はその頃、来迎寺電業所に勤務していて、私が休暇を利用して、その社宅に数日間泊まりに行っていた時のことである。休日にはほぼ決まって釣りに誘う父が、その日はどうしたのだろうといぶかりながら後に従った。小一時間ほど、なだらかな丘の斜面を、土器はないものかと歩き回ったが、結局見つからない。見つかりそうもないから、もう帰ろうということになった時、突然「ケッケーン・ケーン」という甲高くけたたましい鳴き声に驚かされた。「メス」を呼んでいるのか、縄張りを主張しているのか、何回も繰り返され、初めて聞いたその声に圧倒された。「キジがいるんだよ」と言いながら父も聞き入っていた。それを思い出して絞り出した句だった。 全員が再び集合してから、先生のご批評が始まった。一般の句会なら互選ということかも知れないが、この時は、先ず、5、6句の先生が選ばれた句に対して、どこそこの表現が良い、とか、ここはこうした方がもっと良かった、などのご指導があった。その後、私の句も含めて選ばれなかった句も、すべて一言ずつ批評されたと記憶する。
私の句に対しては「これはわかりませんね。あとで作者に説明してもらいましょう。」とだけのそっけないものだった。私は、あの時、生意気にも、何も説明しなかったと思う。先生ご自身の句が、冒頭に引用した句だったのである。それが読み上げられた時も、「これは僕の作ですから、・・・」と説明も批評もされなかったことを記憶している。しかし雪国生まれの人なら、すんなりと心にしみて来る句である。句会は梅雨入りの頃だったと思うが、冬の季語で始まることから、数ヶ月は温めて来られた作品だったのかも知れない。車道側にうず高く積み上げられた雪に押し潰されそうな気分に耐えつつ歩む。背負い駕籠にあふれるばかりの野菜を入れて向こうから近づいてくる腰の曲がりかけた老女。すれ違う二人組の女子高生にも、笑いを交えた会話は無い。先生が退勤されるお姿もあった。そんな雁木を、二枚歯の高下駄でカラン・カランと音を立てながら通学していた自分がいた。上ノ山から赤坂を下ると雁木が始まり、旭橋の手前の坂道の上まで続く。橋を渡れば、やや新しい天井の高いアーケード風の雁木が再び現れ、小千谷駅方向に曲がる三叉路までで終わる。そこまで来ればあと三分程で谷高の校門である。いつ頃からか知らないが、私の父も句作をやっていて、「花守」にも何回か参加させて貰って、先生のご指導を受けていた。父が亡くなってしばらくして先生にお会いした時、「お父さんの句集を出しておあげなさい」と勧めていただき、「薬喰」を編纂した。その過程で、父の句帖の中に次の句を見つけて、あの時のものに違いないと直ぐに確信した。
雉は啼き土器は太鼓の眠りかな 虎杖
「雲母投句控え昭53.1」とのメモがそえられていたので、あの時から二十年は経っている。実際に詠んだのはもっと前だったのだろうと思う。それとも長年の病床を経て、昔を思い出して詠んだのだろうか。この句が先生のお目に留まっていたとしたら、どんなご指導を下さったのだろうと思いめぐらしたものである。 谷高を卒業して小千谷を出ることになり、あの歌会も辞した。先生のご指導の下での句会も、あの時の一回限りで、その後開かれたということは聞いていない。学校も会社も工学系を選んだこともあって、句作は勿論、歌作も遠ざかるばかりだった。句集や歌集を読むのは好きだったが、自ら詠むことは殆ど無くなって、定年を迎え、高齢者の仲間入りをした。しかしその間、なぜか「雁木行く・・・」の句だけは、頭から離れたことは無かった。
[補遺1]「散木抄」に「教科書調査官の七年半」という章があり、先生はその中(130頁)で次のように述べておられる。「元来、教科書は著者と読者(生徒)の間に先生が介在する点で、一般図書と別個の正確を持っている。一般図書は著者と読者の直接の対話であるが、教育では対話は先生と生徒が行うもので、教科書はその「道具」にほかならない。したがって教科書は個性発揮の場ではなく、先生の自由な授業の便宜をひたすら配慮すべきもので、そこに多少とも著者の個性が抑制されるのは常識であろう。」 先生の谷高における「日本史」講義は、まさに前記のお考えを具現したものであった。そして、授業時間内にもかかわらず図書館で過ごす自分に、何も言わずに受け入れて下さった目﨑・田近の両先生には、「分っていただいていたのだな」と何十年も経てから安堵し感謝したことを覚えている。
[補遺2]「無用者の系譜」初版は、昭和39年4月に筑摩書房から発行された。しかし、その著者あとがきには、その著作が「昭和34年2月発行の新潮社版「日本文化研究」第2巻に載せたもの」と書かれてあり、目﨑先生に冊子が届いてから間もない時期に一致する。一方、先生の『漂泊 日本思想史の底流』は昭和50年4月に角川選書78として発行されたが、先生もまたそのあとがきには、「『漂泊の思想史』と題した初稿を、学友沢木欣一兄を中心に発行されている雑誌「風」に載せたのは昭和23年、思えば二十代半ばのことであった。」ときされている。唐木氏が『風』を読まれていたかどうかは不明で、引用もないが、先生の角川版には、本文中に「唐木順三」の名や「無用の漂泊」といった語句もあることから、「無用者」を「漂泊」の範疇でとらえられていたことは間違いない。新聞の書評か何かで『漂泊・・・』の発行を知った私は、買い求めて欧州行きの機中で目を通した。そして確信したのだが、あの時先生のご機嫌が良かった理由が、親友・沢木欣一氏が送って来てくれたからなのか、唐木氏が発行前の著作に批評を求めて来たからなのか、生涯のテーマをさらに膨らませて『漂泊・・・』を上梓するご決心のキッカケになったからなのか、それともそれらすべてだったからなのか・・・。今となっては確かめる術がない。
平澤邦夫さんは第10回卒の人達の中でも記憶に残る人でした。私が高校2年生の夏休み前、図書部に入った時の部長で一ヶ月後に実施された図書部の国立国会図書館見学一泊旅行に一緒に参加した。現在の迎賓館が図書館時代だった。その後に白鴎高校の図書館にも回った。平澤邦夫さんのこの文章は堀澤祖門師が編集されていた冊子「柏葉」に投稿されたものだが、昭和34、5年頃の図書館の雰囲気を良く出しているのでお借りした。邦夫さんは昨年重篤な闘病生活に入られた旨の長いメールを頂いた。日立の重電部門の仕事をされ大変レベルの高い仕事をされたと聞いたことがある。一度東京舟陵会の記念講演をして欲しい一人だった。
「小千谷高校60年史」の中の記事に、昭和33年4月、美しい図書館が完成した。この図書館建設に当たって、金子鋭氏(富士銀行頭取)は年々2万円を寄贈、池田恒雄氏(ベースボールマガジン社社長)は前後合わせて1200冊の蔵書を寄贈したとある。平澤邦夫さんはこの年に入学し、私も翌年入学した。この図書館の運営を目﨑徳衛先生と田近正司先生が担ったのだが、他の先生方も加わり図書館自体が素晴らしいアカデミックな雰囲気を持っていた。この当時を良き思い出として偲ぶ人は平澤邦夫さん以外にも沢山おいでである。本当に魅力のある時代だった。(佐藤弘吉)
| 1 目﨑徳衛先生の評伝出版記念会へのお誘い | 堀澤祖門 | 旧制中学41回卒 |
|---|---|---|
| 2 実録・小千谷高校野球部物語 | 上村敬介 | 高5回卒 |
| 3 一度だけの句会 | 平澤邦夫 | 高10回卒 |
| 4 オペラを小千谷で今秋予定(小千谷新聞掲載) | 品田広希 | 高58回卒 |
| 5 俳句と短歌 | 小山雄一、 佐藤弘吉 |
高13回卒、高11回卒 |